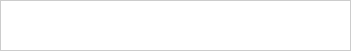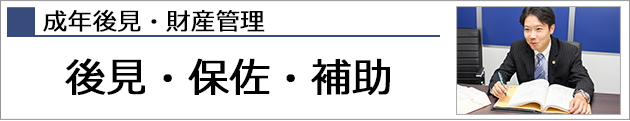

法定後見制度は,家庭裁判所から選任された後見人等が,事理弁識能力が無くなったり,乏しくなった本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援する制度をいいます。
法定後見制度には,本人の判断能力の程度に応じて,後見,保佐,補助の3種類が設けられています。後見・保佐・補助の違いは,以下に見るように,主として後見人等の代理権と取消権の範囲の広狭です。
| 後見 | 保佐 | 補助 | |
|---|---|---|---|
| 対象となる者 | 事理弁識能力を欠く常況の者(日常の買物もできない) | 著しく不十分な者(不動産の売買など重要な財産行為はできない) | 不十分な者(重要な財産行為は誰かに代わってもらった方が良い) |
| 申立てをすることができる人 | 本人,配偶者,四親等内の親族,検察官など 市町村長(注1) |
||
| 後見人等の同意が必要な行為 | - | 民法13条1項所定の行為(注2)(注3)(注4) | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)(注1)(注2)(注4) |
| 取消しが可能な行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 同上(注2)(注3)(注4) | 同上(注2)(注4) |
| 後見人等に与えられる代理権の範囲 | 財産に関する全ての法律行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注1) | 同左(注1) |
| 制度を利用した場合の資格などの制限 | 医師,税理士等の資格や会社役員,公務員等の地位を失うなど | 同左 | - |
(注1)本人以外の者の請求により,保佐人に代理権を与える審判をする場合,本人の同意が必要。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じ。
(注2)民法13条1項では,借金,訴訟行為,相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為が挙げられている。
(注3)家庭裁判所の審判により,民法13条1項所定の行為以外についても,同意権・取消権の範囲を広げることができる。
(注4)日常生活に関する行為は除く。
後見人等の選任は家庭裁判所の判断
後見・保佐・補助のうち,どの類型にあたるかは,医師の診断をもとに家庭裁判所が決めます。本人の判断能力を測る検査方法としては,長谷川式簡易知能スケール(HDS-R)や認知機能検査(MMSE)が広く用いられています。例えば,ある裁判所では,目安として,HDS-Rで10点以下又はMMSEで14点以下だと後見,HDS-Rで11点以上15点以下又はMMSEで15点以上17点以下だと保佐,とされているのが参考になります。
また,後見人等を誰にするかについては,家庭裁判所が判断して決めることになります。例えば,親族間で本人の財産管理をめぐって争いとなっている場合,親族以外の第三者との間で紛争が生じている場合,管理財産が多額又は複雑な場合などでは,親族ではない専門職が後見人等に選任される可能性が高いといえます。なお,家庭裁判所の後見人等の人選に対しては,不服申立てはできません。